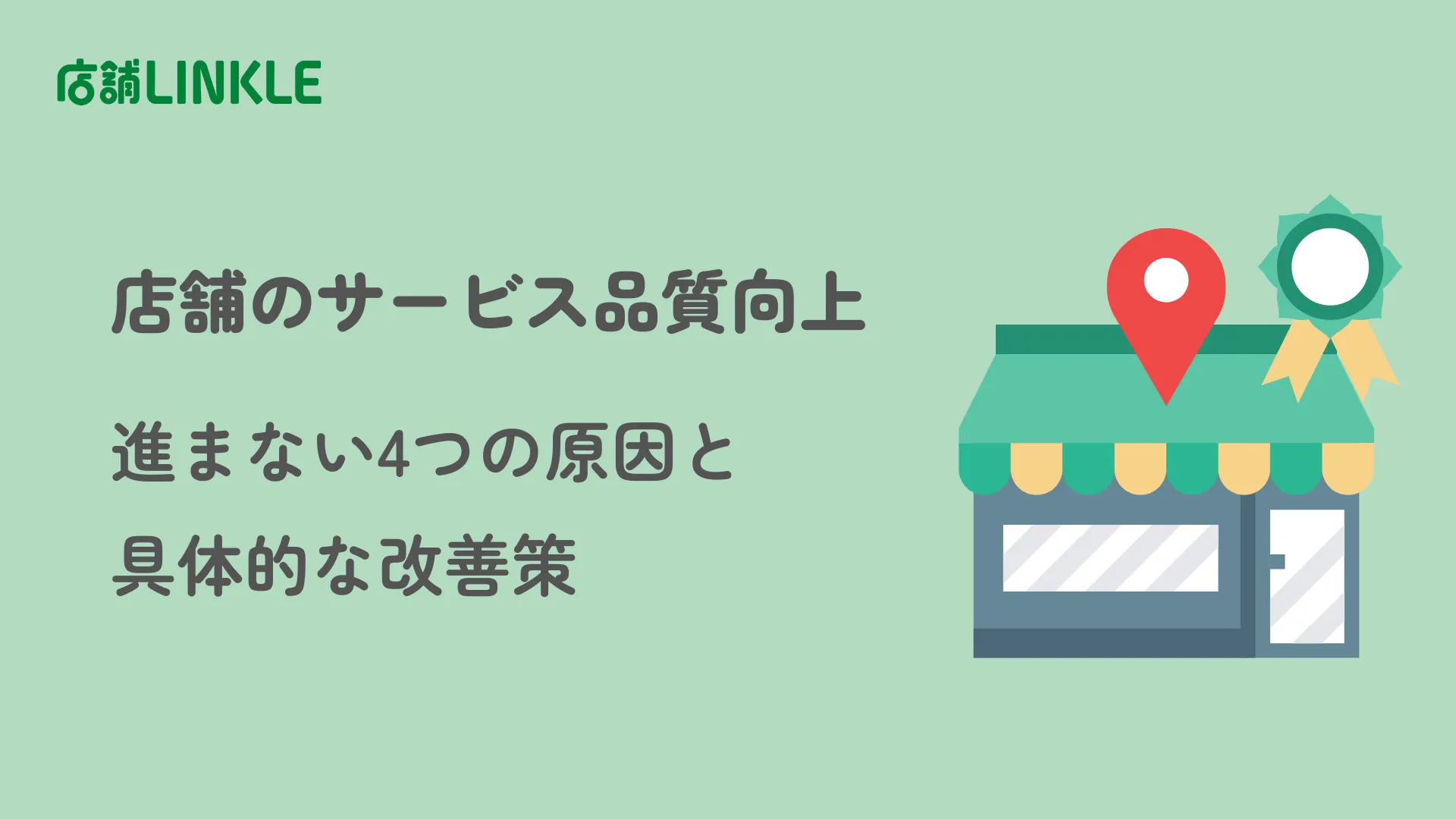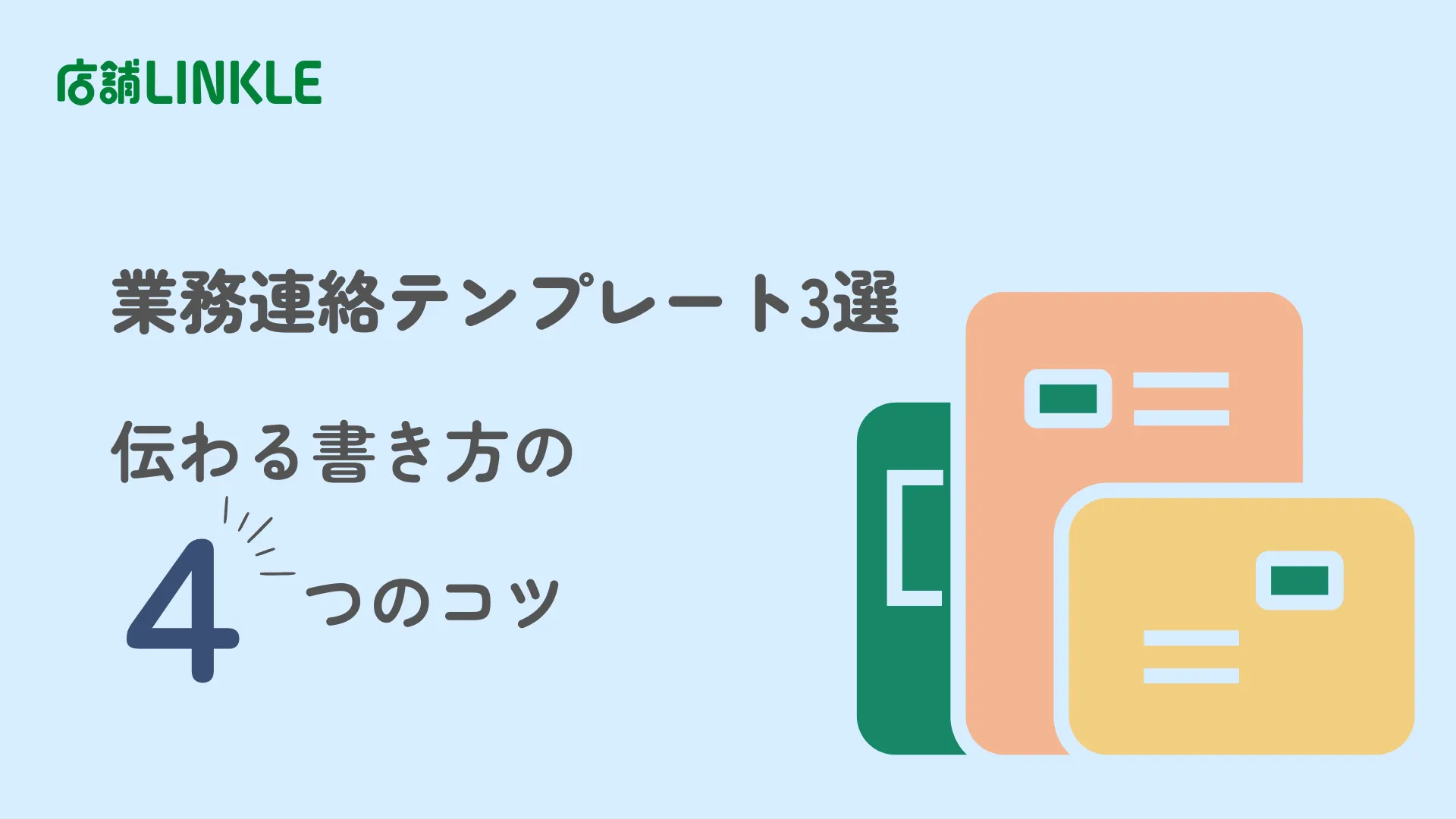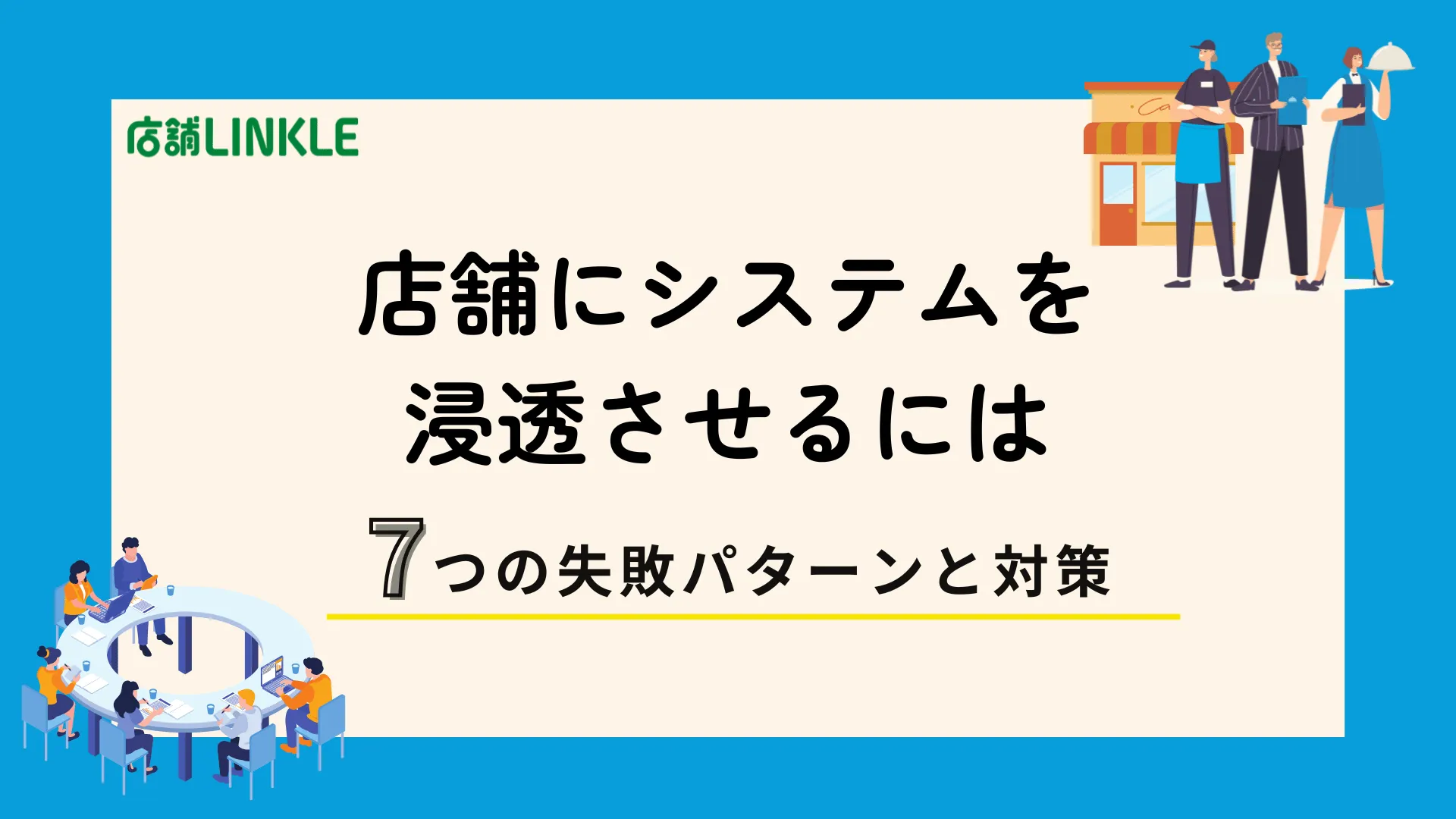
店舗にシステムを浸透させるには
こんにちは。
企業のIT投資は増加傾向にあり、小売・卸業においても2026年度予測は122.9%増(2021年度比)という調査※もあります。
一方で「せっかく店舗に導入したシステムが浸透しなかった」というシステム導入担当の方々もいらっしゃるのではないでしょうか。時には「経営層から導入システムの活用度について突っ込まれた」という担当者のお話も伺います。
セオリーに則りヒアリングを重ねた上で要件定義し、機能比較を経て導入したにも関わらず、なぜ店舗に定着しないのか。そこで今回は見落とされがちな「店舗にシステムが浸透しなかった7つの失敗パターンと対策」についてご紹介します。
※引用:株式会社富士キメラ総研:『業種別IT投資/デジタルソリューション市場 2022年版』https://www.fcr.co.jp/pr/22094.htm
目次
システムが定着しないパターンと対策7点
「どのタイミングで何をしておけば避けられたか?」、実際にあった失敗パターンを「準備→選定→決定・導入初期→運用・定着」フェーズ別に整理しました。
STEP1.準備フェーズ
- 選定前の導入目的の設定と共有が、以後のフェーズに影響します
- システム導入の際は、一般的に業務をシステムに合わせることで効率化が進みます。一方で業務の内容や店舗数によっては、システムを企業の運用に合わせる必要があります。
「何を変え、何を残すか」の見極めには現場の話を掘り下げることも必要です。加えてシステム側でどこまで業務に寄せられるのかを、早い段階でベンダーと確認しておくことも、導入後の柔軟な運用につながります。
❶店舗にヒアリングしても具体的な話が出てこない、導入後に不満や要望が出てきた
・対策
アンケートなどのテキスト形式によるヒアリングだけで終わらせない。店舗スタッフも含めた検討チームの発足や座談会の実施など、会話の流れでスムーズに言語化させる。1問1答だけでなく、日々の業務の流れを雑談的に話してもらうと、会話の流れで課題が見えやすい。
❷店舗の要望や課題の「背景」まで掘り下げが足りず、解決手段や選定の基準がずれていた
・対策
店舗スタッフが「具体的にどういう状況で、なぜそう思ったか」まで深掘りする。幅広い属性のメンバに話を聞いて、ヒアリング内容が一人の感想なのか、それともスタッフに共通する課題かどうかを確かめる(店長以外の新人、複数店舗経験者など)
❸拡張性について確認せず、後になって自社固有の業務や、運用の変更時に支障が出た
・対策
事前にシステムの柔軟性・拡張性について、ベンダーに確認する。その際、過去の対応実績やカスタマイズ方針、支援体制についても確認しておく。
STEP2.選定フェーズ
- 現場で定着するシステムかどうかは、このフェーズでほぼ決まります
- 選定初期に機能比較表を作成する企業が多いですが、高度な機能や機能数だけを基準に候補を絞り込みすぎると、導入後に現場とのギャップが発生することがあります。本部や店舗のユーザとシステムとの相性についても検証する必要があります。
❹操作や画面が複雑で店舗スタッフが直感的に使えなかった
・対策
実際に使う店舗スタッフが触るテストの機会を設ける。テストは複数名で行い、「ある程度スタッフ自身で操作を進められるか」、「年齢層の高いスタッフも読みやすい文字サイズか」などの操作性、視認性も確認する。
参考:株式会社マルイチ様導入事例:商品部から各部門担当への通達を徹底
https://hscproduct.com/tenpo/casetl/675/
システム選定の際に、「店舗スタッフ」の使用感を重視されたお話についても掲載されています。
STEP3.決定・導入初期フェーズ
- 導入時の混乱や現場の負担は、ここでの進め方次第で大きく変わります
- 最初の段階で運用が混乱していると、店舗スタッフのシステムに対する抵抗感が強まります。苦手意識が生まれないよう、スムーズな立ち上げに向けた準備が求められます。
➎試験運用なしで一気に全店舗に導入して、現場が混乱した
・対策
モデル店舗でパイロット導入し、課題を洗い出してから展開する。パイロット導入中に見つかった課題は、マニュアルや運用改善に落とし込む。複数機能をもつシステムを導入する場合は、段階導入も検討する。
❻移行期間の運用ルールがあいまいで元に戻ってしまい、本部が対応に追われた
・対策
移行期間に関する対応と期限を明確に定めて周知する。「やっぱり前のやり方の方がやりやすい」と旧運用で押し通す店舗に対しては、一定期間を過ぎたら差し戻す、そもそも受付しない対応をとる。
STEP4.運用・定着フェーズ
- 「導入して終わり」ではなく、「継続的に使われる」状態がゴールです
- 実際の使い勝手や運用負荷を継続的に把握し、改善していく仕組みが不可欠です。
建設的なシステムへの意見は意識しないと店舗から吸い上げにくいため、意図的にフィードバックの仕組みを構築する必要があります。
❼店舗からの声を集める仕組みがなく、改善が進まなかった
・対策
店舗の要望を集める場や窓口を設け、気付いたときに定期的に上げられるようにする。本部はログイン状況や活用状況をモニタリングしたり、定期的にアンケートをとって店舗のフィードバックを集める。
まとめ
ここまで4つのフェーズに分けて、「実はシステムの定着を左右するポイント」をご紹介しました。システム選定には、「店舗の実態に精通した現場視点」と「導入担当者の全体的・長期的な管理視点」の両方のバランスが保たれている必要があります。
店舗Linkleは長く活用いただけるシステムを目指して、店舗スタッフが抵抗なく使える「シンプルな操作感」を重視すると同時に、企業独自の運用も踏まえた「個別改修のご提案」もしております。
システムの検討にあたって、社内ヒアリングや運用設計などでご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。