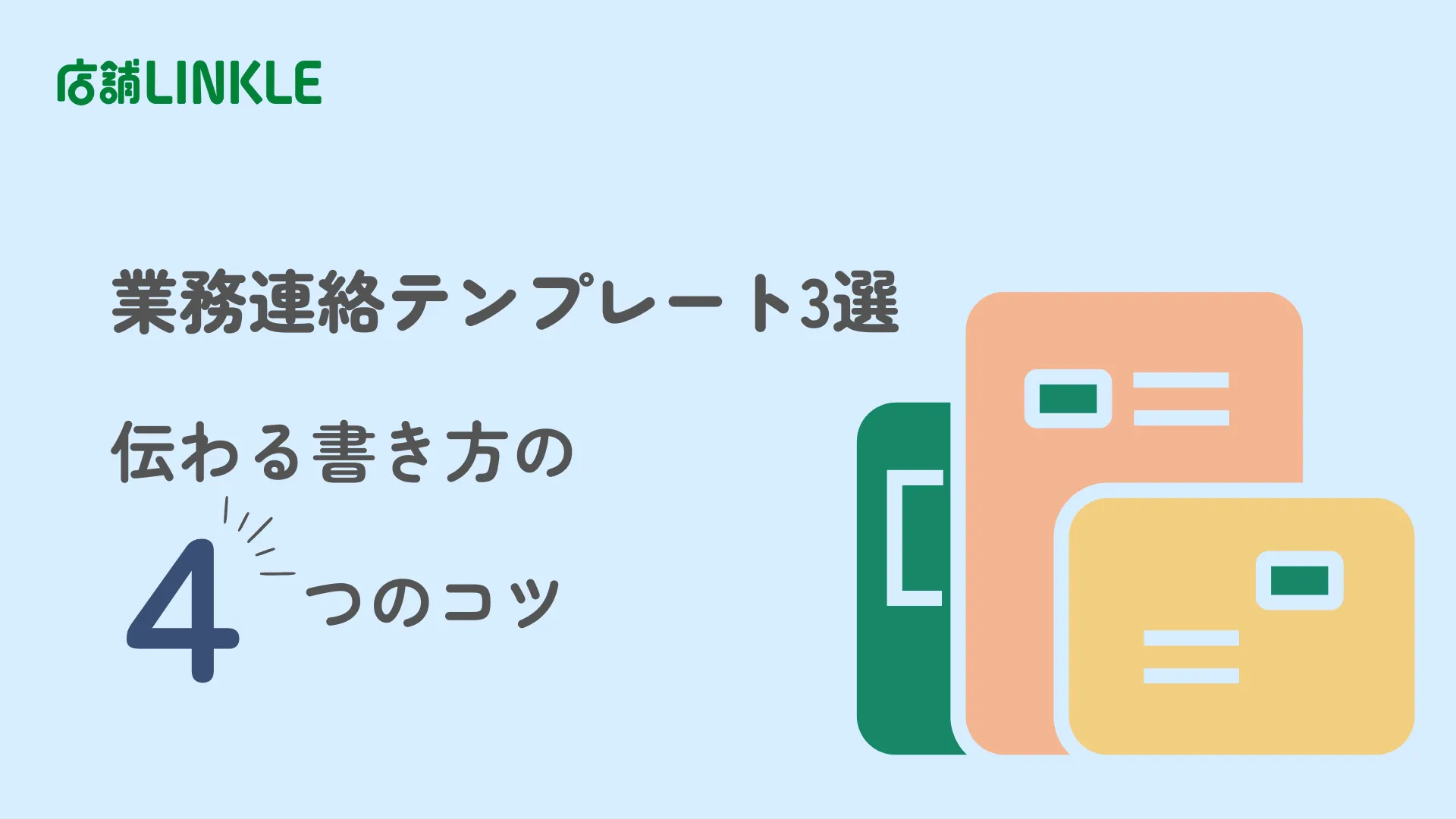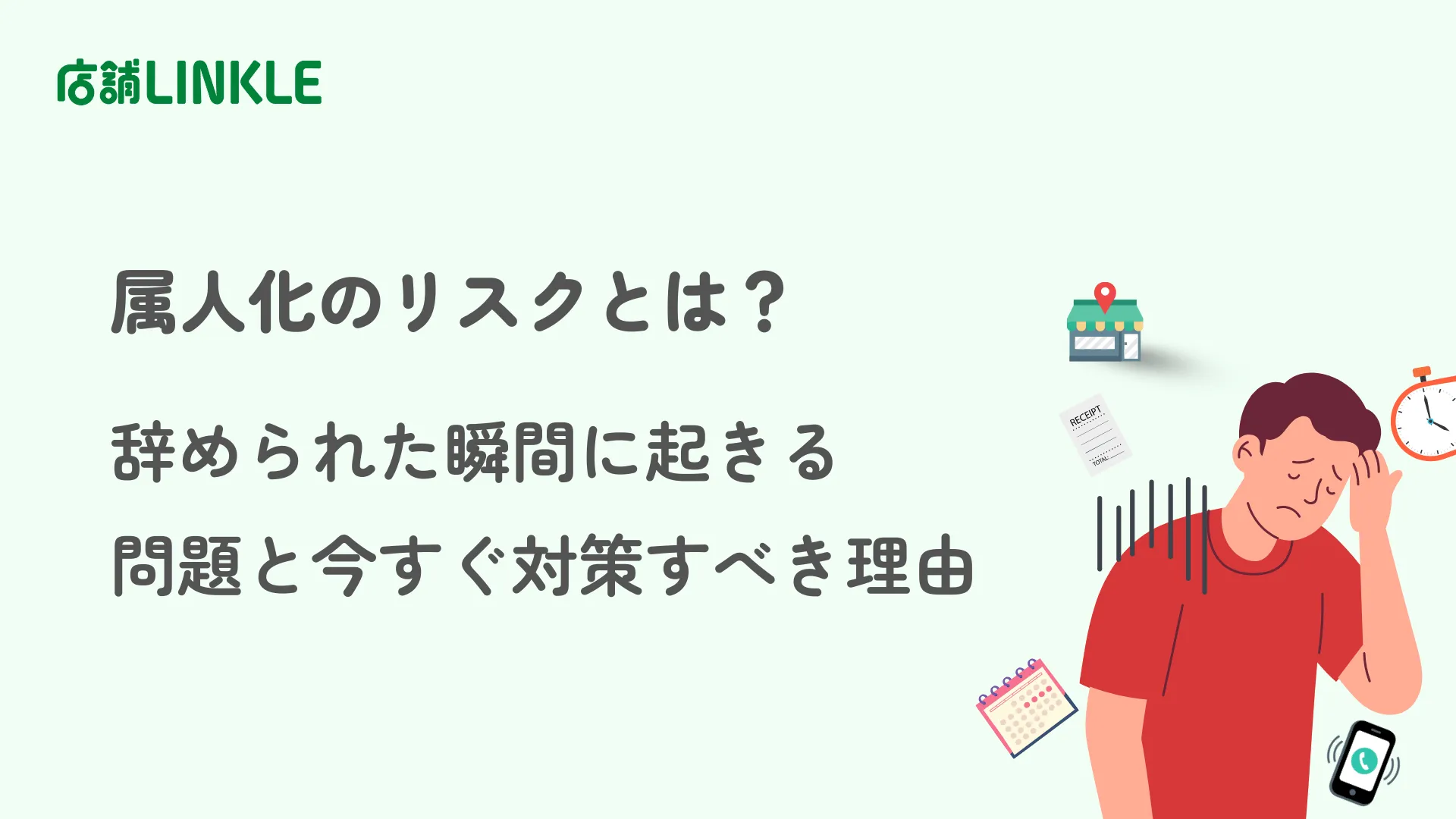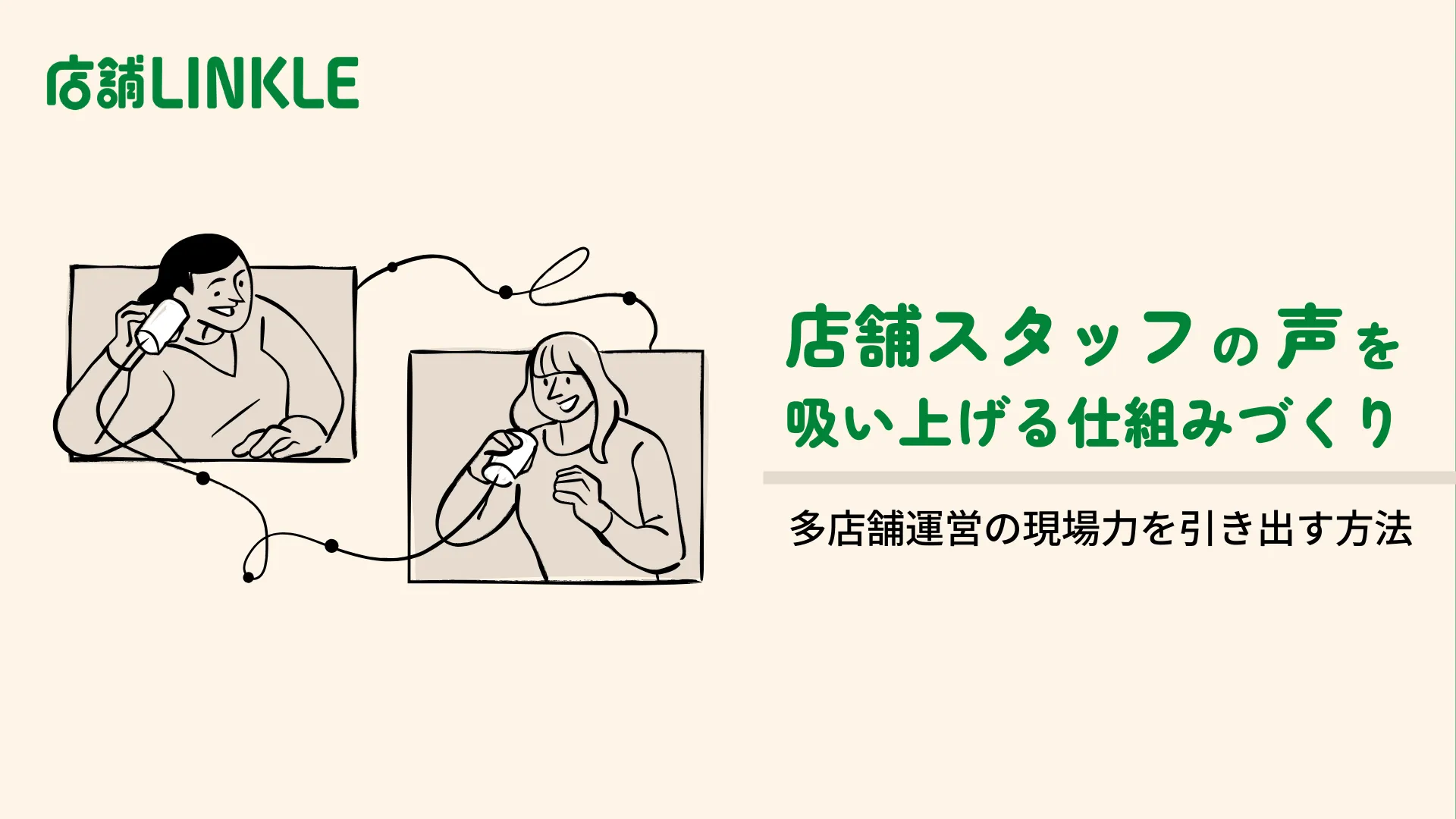
店舗スタッフの声を吸い上げる仕組みづくり|多店舗運営の現場力を引き出す方法
目次
はじめに:現場の声が埋もれていませんか?
店舗スタッフの声には、売場改善や業務効率化のヒントが詰まっています。
しかし、「現場から声が上がってこない」「良い取り組みが他の店舗に広がらない」と悩む企業も多いのではないでしょうか。こうした課題を放置すると、改善のアイディアが埋もれ、全社的な生産性向上や顧客満足度の向上につながるチャンスを逃してしまいます。
改善するためにはまずはスタッフが安心して気軽に意見を出せる環境をつくり、現場の声に対する「評価」まで行うことが重要です。
そこで今回は現場の声を継続的に集め、「評価」までの流れを仕組み化するポイントをご紹介します。
なぜ店舗スタッフの声が埋もれてしまうのか?
現場の声が集まらず活用が進まない原因は、主に以下の通りです。
- 属人化
- 発信のハードル
- フィードバック不足
- メリット不在
以下に詳しくご紹介します。
属人化
属人化とは、業務のやり方やコツ、トラブル対応の知見などが特定の個人にひもづき、その人がいないと再現できない状態です。 たとえば、一部の店舗スタッフだけが売場づくりの工夫やギフトラッピングのコツなどを知っている状態だと、そこに依存してしまいます。 これがまさに属人化です。
この状態になると、スタッフの貴重な知見が他店に水平展開されず、個人のメモや口頭での会話などに留まってしまいます。 そして、特定の人が異動や退職した場合、その知見が同時に消えてしまいます。
発信のハードル
発信のハードルとは、現場スタッフが声を上げにくい心理的・物理的な障壁を指します。
たとえば、報告内容を整理したり、写真を撮って説明文をつけたりする手間が大きいと、日々の業務に追われる中で発信は後回しになる傾向があります。
さらに、「投稿内容にダメ出しされるのでは」という不安があると、せっかくの気づきも共有されずに終わってしまいます。こうした状態では、本部がどんなに発信を促しても店舗からの発信は期待できません。
フィードバック不足
フィードバック不足とは、現場からの声に対して反応や評価が返ってこない状態を指します。
たとえば、「送った内容が読まれているのか分からない」「何のリアクションもない」という状況が続くと、スタッフは“どうせ見てもらえない”と感じ、発信をやめてしまいます。この状態では、改善提案が活かされず、現場のモチベーションも低下します。
結果として発信はだんだんと減っていき、新しい声を継続的に集めることは難しくなります。
メリット不在
メリット不在とは、声を上げても自分にとって得がないと感じる状態を指します。
たとえば、工夫を共有しても評価されない、逆に「その後の報告もお願い」と追加の負担だけが増える場合、発信は敬遠されます。
また、情報更新の責任を負うことへの不安も、発信意欲を下げる要因です。
このような状態では一部の意欲的なスタッフの発信だけに偏り、多様なアイディアが集まりにくくなります。
なかでも「発信のハードル」と「メリット不在」は、形骸化の大きな要因になります。
実際、弊社は2003年からナレッジマネジメントシステムを提供していますが、導入検討するお客様から、ナレッジの収集や更新に関するお悩みを多く聞かれます。店舗にとっては目の前の運営を優先せざるを得ず、全社的なメリットを考える余裕が持ちにくいのです。
解決のカギは「仕組み化」
店舗の声を活かすには、誰でも簡単に投稿できて、見える化され、モチベーションを得られる仕組みが肝となります。属人的な運用から脱却し、継続的に声が集まり、活用される仕組みを整えることが重要です。
現場の声を継続的に集めるための3ステップ
継続しやすさを考慮して段階的にステップを踏むことが大切です。
ステップ①:投稿をシンプルにする
- 写真や動画をそのままモバイル端末から共有できる仕組みを用意する
- 文字入力は最低限にとどめ、入力内容はテンプレート化する
★Point:最初から詳細な記載を求めると、投稿する文化が根付きません。現場は「あとで整える」くらいの感覚で出せる状態を作るのがコツです。
ステップ②:店舗間で共有し、「見える化」
- 投稿内容は一部の人だけでなく、全店舗のスタッフがアクセス可能にする
- 社内掲示板や共有ツールで公開する
- 「いいね」機能や質問コメント機能で相互に反応できる仕組みを整備する
★Point:店舗同士が直接やりとりして、参考にするにあたって不明な点を質問できる状態だとなおよいでしょう。
ステップ③:評価と承認を仕組みに組み込む
- 月次で「ナイス事例賞」を設ける
- 表彰やインセンティブと連動させる
★Point:評価は「定量的な成果」だけに偏らせないことが大切です。「工夫の着眼点」や「チャレンジ姿勢」にも光を当てることで、発信が広がります。
現場の声を活かした取り組み事例
現場の声を収集して積極的に活用している企業の事例をご紹介します。
食品スーパーの事例
before: 本部と店舗間の連絡手段はメールやLINEにとどまっていた
after: 「店舗Linkle」のコミュニティ機能を活用し、部門ごとにグループを作成。
チーフやサブチーフが、売場画像や販売施策、結果を投稿・共有。投稿には「いいね」やコメントで反応でき、双方向のやり取りが可能に。さらに、半期に一度、最も反響のあった投稿を表彰し、発信のモチベーションを高めている。
引用:商品部から各部門担当への通達を徹底(株式会社マルイチ)
書店の事例
before: 出版市場の縮小が続く中、同社は長年の「トップダウン」運営からの転換が課題。社内では、若手が企画を立案し、幹部が精査・推進する体制の構築が求められていた
after: 自由闊達に議論できる土台を整備。ビジネス知識の教育とともに、店舗・部門・経営陣の社内コミュニケーションの活性化を通じ、若手の提案と幹部の精査・推進を回す「ボトムアップ」体制を定着。赤字スペースの収益改善と新規顧客開拓につながった。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 「現場の声を活かした新事業チャレンジと店舗改革」
靴大型専門店チェーンの事例
before: システムが本部から店舗への一方通行で店舗が返事ができないため、特定の店舗宛、店舗から本部、店舗同⼠の連絡はFAXや電話連絡がメインとなっていたが、店舗同士の情報共有の重要性は感じていた
after: 社員側からの要望がきっかけでコミュニティ機能を使い始めました。プロジェクトごとにコメントし合うことで、【店舗・本部】など所属や役職関係なく気軽に意見交換ができた。店舗間で実施状況や好事例を共有しお互いに高め合えるのが、多店舗展開しているメリット。
引用:<脱電話・ノウハウ共有・実施率向上>を実現!(株式会社シューマート)
まとめ:声の仕組み化が現場力を文化に変える
多店舗運営における競合との差別化の源泉は、現場だからこそ得られる声です。その声を点で終わらせず、仕組みとして循環させることが、企業の成長力につながります。
本記事でご紹介した「投稿のハードルを下げる → 見える化 → 評価」のサイクルを回すことで、スタッフ一人ひとりの声が資産となり、やがて現場力が企業文化として根づいていきます。